 ウキウキ世田谷どっと混む
世田谷区商店街振興組合連合会/世田谷区商店街連合会
ウキウキ世田谷どっと混む
世田谷区商店街振興組合連合会/世田谷区商店街連合会
![]() 用賀商店街振興組合
用賀商店街振興組合
(ようがしょうてんがいしんこうくみあい)
◆商店街の沿革
用賀の中央を走る大山通りは、一方は世田谷・四谷に、一方は江戸に通じており、早くから大山詣での宿場町として栄えてきた。
明治40年4月に玉川電車が開通すると、宿場町的性格を持った用賀駅付近は街道随一にまで発展。また、関東大震災の後人口の流れが郊外へ移るとともに、用賀の人口も増加した。
昭和8年、用賀の時計商・小倉卯之助を会長として商工会が設けられたが、統制経済移行の中では本格的な活動は出来なかった。
昭和18年に完成した玉川前円耕地整理により、碁盤目状に整備された用賀には住宅が急増、商店も住民を対象としたものに変貌。同年誕生した用賀中町通り沿いに商店が増加し賑わっていった。こうして昭和22年、戦後の混乱の中、48店で用賀商工会が誕生、初代会長に鈴木直次が就任した。
昭和44年、玉川電車は国道246号線改善のため廃止となり、人の流れは大きく変わっていった。昭和52年4月新玉川線の工事も完成、さらに平成5年10月竣工の世田谷ビジネススクエアは用賀駅と直結し、一日の乗降客は6万人以上に及ぶ。
振興組合の設立計画は昭和51年から協議が進められ、昭和63年3月、創立総会にて承認され、4月より業務を開始した。
平成13年3月にショッピングプロムナード整備事業が完成。
◆商店街の現状
平成20年、商店街振興プラン策定。消費者/会員向けにアンケート調査、地域の現況調査を実施。平成21年度、振興プランに基づき、アンテナショップ、まちのステーション事業を開始。(21年度地域商店街活性化事業補助、商業活性化事業に係る計画認定)同時に、まちづくり会社を設立。
22年度より、(中小商業活力向上事業補助)「個店の魅力アップ」「共同販促の充実」「施設等有効活用」の三事業を開始。
◆今後の展望
想定する商圏には6万人の人口がある。「安全で、安心で、楽しい商店街」として、地域に貢献する一方、参加組合員の士気を高め、商業を大いに盛り上げるような、商店街事業を研究・推進する。

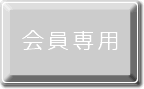

 (公財)世田谷区産業振興公社
(公財)世田谷区産業振興公社
