 ウキウキ世田谷どっと混む
世田谷区商店街振興組合連合会/世田谷区商店街連合会
ウキウキ世田谷どっと混む
世田谷区商店街振興組合連合会/世田谷区商店街連合会
世田谷地区
【下馬一丁目商店会】
- 商店街の沿革
昭和27年に40店で下馬一丁目商店会は設立しました。目的は、会の発展をはかるための共同事業、親睦と福利厚生、会員の経営及び技術の改善向上でした。
昭和30年代に中元歳末売り出しを開始(売り出し部)、90基の街路灯設置(街路灯部)、後半加入125店でした。
昭和40年代に金融部を設立、会が資金を調達し各店希望者に日掛返済による小口融資を始める。また簡易保険、団体加入開始、年間7%割戻し、加入者5%、商店会手数料2%、会の収益となる。
昭和50年代には、中元歳末売り出しに若手の発案により不参加店からも1店千円程度の商品を寄付してもらい、商店賞として加え、商品が多くなり好評でした。
平成3年、売り出し部が、中元歳末売り出しの参加店減少により中止、平成4年、金融部、借り入れ利用者の減少により中止。
平成8年、街路灯建て替え工事47基に区の補助金を受ける。
- 商店街の現状
昭和30年代から40年代は、店舗数も増え(125店)中心部では生鮮3食品をはじめ食品店が軒を連ね、賑わいをみせていましたが、40年代後半から各駅辺の(渋谷、三軒茶屋、祐天寺、学芸大学)商店街の整備が進み、4方を山に囲まれた谷間のような状態になり、陰りがみえはじめ、加えて経営者の老齢化、後継者不足により閉店する店が出始めてきました。
昭和40年代は125店舗、昭和52年110店舗、平成2年82店舗、平成12年42店舗。
現在はコンビニの進出により各店とも、自分の生活を守るのが精一杯で、商店会活動に参加できる状態ではなく、親睦団体の域を出ないのが現状です。
- 今後の展望
共通商品券も三軒茶屋方面での使用が多く、当会ではあまり出回らず、各店の共同体意識はきわめて薄いのが実状です。
今後は、経営者の半数が60代のため、5~10年後には20店舗前後に減少するのではないかと危惧しております。

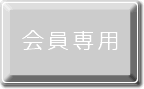

 (公財)世田谷区産業振興公社
(公財)世田谷区産業振興公社
